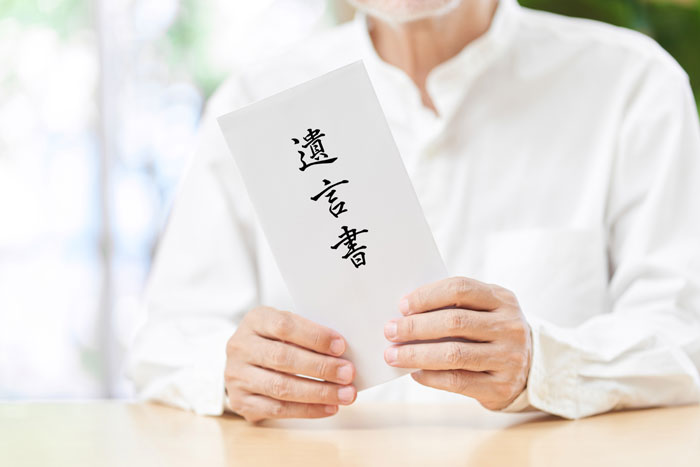
遺言書とは、相続に関する事柄をまとめた法的な効力がある書類のことです。
財産をお持ちの方が亡くなられた後、遺されたご家族に対し誰に何を引き継いでほしいかという意思を伝える最良の手段になります。
また、生前、親身に介護をしてくれた子どもの配偶者など本来相続する権利のない方へ財産を渡すこと(遺贈)も可能になります。
反対に遺言書がなければ、相続人同士のもめごとや混乱が起こり、遺された大切な家族の関係が悪化するおそれがあります。
そうならないためにも、ご自分の想いを遺言書という形で残しておいたほうがよいでしょう。
このページの目次
1.遺言書の種類
遺言書には
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
どの遺言書でも要件を満たせば法的に有効となりますが、それぞれ作成方法が異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言を残す方)自身が手書きで作成(自筆)した遺言書です。
ただし、財産目録については、2019年の民法改正によりパソコンで作成したものや通帳コピーなども認められるようになりました。
自筆証書遺言は、ほかの2つの遺言書作成では必要になる証人が不要で、署名押印は本人のものだけで作成できます。
しかし、自筆証書遺言として必要な内容や形式などの要件を満たしていない場合、無効になるリスクがあることに注意しましょう。
また、自筆証書遺言は遺言者が自分で保管することになっていましたが、2020年7月から法務局で保管する制度が始まりました。
これまでは遺言者の死後、家族に見つけてもらえなかったり、紛失や改ざんといったリスクがありましたが、この制度を利用するとそのようなリスクを防ぐことができます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書です。
公正証書遺言を作成する際には、遺言者が遺言書を書いたことを証明する証人が2人以上必要になります。
未成年や相続人などの関係者は証人にはなれないため、利害関係のない第三者に依頼する必要があり、知人のほか、専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に依頼する方法が一般的です。
公正証書遺言書には本人・証人・公証人の署名押印が必要になり、原本は公証役場に保管、正本(原本の写し)は本人が保管します。
また、公正証書遺言書を作成する場合には、財産の価額に応じて手数料がかかります。
例えば、財産の価額が500万円超1,000万円以下の場合は17,000円、1,000万円超3,000万円以下の場合は23,000円と段階的に増加していきます。
詳細は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言書の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
遺言書を自分で作成・署名押印し、封筒に入れたあと押印します。
公証役場で公証人と証人2人以上に秘密証書遺言だという確認をしてもらい、その封筒に証人、公証人の署名押印をしたあと、遺言書を持ち帰り自分で保管します。
秘密証書遺言のメリットは、遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことができる点です。
しかし、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠け、相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となりますが、仮に誰かが家庭裁判所の検認手続前にこの秘密証書遺言書を開封してしまうと、その遺言は無効となってしまいます。
秘密証書遺言については、無効になるリスクが大きいことや手続きの手間の割にメリットが少ないため、現状はほとんど利用されていない状況です。
2.遺言書作成の専門家
上記1では遺言書の種類について見てきましたが、やはりご自身で作成するには難易度が高い、または費用を払ってまで専門家に依頼するまでもないなど、人によって考え方はさまざまです。
ここでは、専門家に依頼するメリットデメリットと専門家の選び方について検討したいと思います。
メリット
専門家へ依頼するメリットは、専門家目線でのリスクやトラブルについてアドバイスを受けながら、法的に有効な遺言書が確実に作成できる点です。
相続にはそれぞれ特殊事情があります。
個人では思いつかないリスクが潜んでいる可能性があり、また遺言書作成においては詳細なルールがあることから、内容に一つでも不備があれば無効になる恐れもあります。
このような不安を払拭しながら安心・安全な遺言書を残すことができるというのが専門家へ依頼する最大のメリットです。
デメリット
唯一のデメリットは費用がかかるという点です。
昨今では多くの情報をネットで収集でき、また遺言に関する制度も整備されてきているため、個人で作成することの難易度は以前より低くなりました。
しかしながら、相続発生後のリスクを抑えながら一切不備のない遺言書を確実に作成するためには、費用をかけてでも専門家へ依頼する意義は大きい気がします。
どの専門家が適任か?
一概にどの専門家が遺言書作成に優れているとは言えません。
例えば、相続財産に不動産が多く含まれる場合は司法書士、相続発生後に相続人同士で争いが予想される場合は弁護士、簡易的な内容で比較的費用を抑えたい場合は行政書士など、個別のケースで最適な専門家は変わってくると思います。
まずは、遺言書作成の業務を一定程度経験している専門家のもとへご相談にいかれて、話しやすく信頼できる方へ依頼するという判断基準で良いのではないでしょうか。
3.遺言執行について
遺言書は、無事に法律上有効な内容のものを完成させたとしても、それで十分ではありません。遺言者(遺言を残す方)が亡くなった後に、遺言に遺したその遺志を実現させるには、
相続人全員が協力してさまざまな相続手続きを進めていく必要があります。
しかし、相続人の中に非協力的な方や消息不明な方がいたりする場合は、思うように手続きが進まず、「遺言執行者」が必要となってくるケースがあります。
遺言執行者とは、「遺言の内容を実現するために手続きを行う人」のことであり、さまざまな権限や義務があります。
遺言執行者は生前に遺言書の中で指定することもできますが、指定されていない場合は、相続開始後に相続人から家庭裁判所への申し立てを行うことにより指定してもらうこともできます。
法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができない(民法1009条)とされていますが、それ以外であれば信頼できる知人友人や相続人のうちの一人でもなることができます。
ただし、相続税が発生する場合は、複雑な相続手続きを10ヶ月という期限内に行う必要があり、相続人間で揉めたりすると収集がつかなくなるケースもあります。
そのため、遺言の中で遺言執行者を決めておく場合、一般的には第三者である弁護士や司法書士、税理士など相続に関する知識を持った専門家に依頼する方が最良な選択といえるでしょう。






