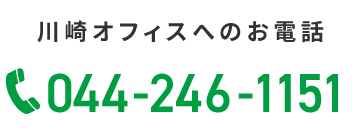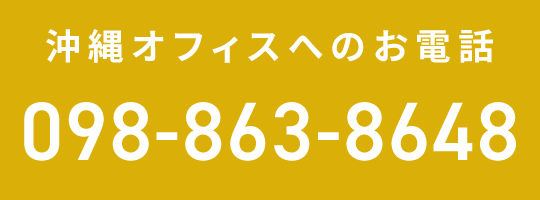相続税は、生前におこなう対策次第で、大幅に負担を軽減できる可能性があります。
「相続する財産がそれほどないから…」と相続対策をしないでいると、予想外に高額な相続税負担に驚いたり、親族間での相続トラブルが発生したりするケースもあるため、遺族に負担をかけないためにも、相続対策は早いうちから始めておくことをおすすめします。
ここでは、知っておいて損はない相続対策の基本を紹介します。
このページの目次
1.生前贈与
配偶者や子ども達に財産を引き継ぐ方法として、相続以外に生前贈与があります。
相続税と贈与税は密接に関係しており、生前贈与とはその名のとおり、財産を所有している方が生きているうちに行う贈与のことです。
生前贈与についても贈与税がかかる場合がありますが、対策をしないで相続税を負担する場合と比較して、トータルでは税負担の軽減につながるよう、さまざまな制度を活用することが可能です。
以下では、生前贈与の概要や贈与税の負担を軽減できる制度、相続時精算課税制度、生前贈与をする際の注意点などをご紹介します。
暦年贈与
贈与税には、受贈者(財産をもらう者)一人につき年間110万円の基礎控除があります。
つまり、110万円までの贈与は非課税になり、その制度を利用して財産を移転していくことを暦年贈与といいます。
ただし注意事項もあります。例えば、「今年から10年間、毎年100万円ずつ贈与する」という約束(契約)の下で贈与を行うと、1年間のうちに一括で1,000万円を贈与したとみなされ、非課税枠を利用した節税メリットを享受できなくなります。
相続時精算課税制度
①制度の概要
生前に行う贈与には2種類あり、一つは上記で述べた110万円の基礎控除を適用した暦年贈与、もう一つは「相続時精算課税制度」です。
相続時精算課税とは、60歳以上の親から18歳以上の子または孫へ贈与する際に2,500万円まで贈与税が非課税になり、2,500万円を超える部分について税率20%の贈与税が課されます。
ただし、この制度を適用して引き継いだ財産については、相続発生時に相続税の課税対象として足し戻すので、完全に課税を回避することはできません。また、一度この制度を適用すると先に説明した110万円の基礎控除を利用する「暦年課税」を選択することはできなくなります。
②当制度のメリット
当制度は相続税の負担軽減にはなりませんが、生前に、しかも短期間のうちに一括で贈与したい資産がある場合には有効です。
さらに被相続人(亡くなった方)の相続財産全体が相続税の課されない範囲内であれば、無税で生前に贈与を済ませることができます。
また、当制度で受贈した土地や建物については、相続時に足し戻す際の評価額は、贈与時の評価額となります。
よって、土地や株式など生前と比較して将来の相続時に値上がりしそうな資産については、その値上がり分については節税効果が見込めます。
ただし逆も然りで、将来値下がりした場合も、贈与時の高い評価額で相続税を計算することになります。
複数のメリットとデメリットがあるので、当制度を適用する場合はよく検討して選択する必要があります。
居住用財産贈与の配偶者控除
自分の死後、遺産分割で配偶者にきちんと自宅を相続してもらえれば安心なのですが、必ずしも希望どおりにはいかない可能性があり、生前に贈与するにも贈与税の懸念があります。
自分が死んだときに配偶者にきちんと自宅が残るようにしたい方のために、「居住用財産贈与の配偶者控除」という特例があります。
この制度は、居住用不動産またはそれを購入するための資金について2,000万円まで非課税になるというものです。
さらに、通常は相続開始3年前に贈与された財産については相続時に足し戻される(相続税の対象になる)わけですが、この制度適用による2,000万円の非課税枠については、そのような対象にはなりません。
つまり配偶者への2,000万円までの贈与については贈与税や相続税がかからないというわけです。
注意点としては、同じ配偶者からの贈与は一生に一度だけ、登録免許税や不動産取得税は通常どおり課税されます(相続の場合、原則、不動産取得税は非課税、登録免許税は軽減されます)。
また、相続税申告時にも「配偶者控除」という特例があり、生前に贈与税の配偶者控除を適用する目的が相続税の負担軽減であるという場合には、あまりメリットがない可能性もあります。
贈与の特例(非課税制度)
住宅取得等資金の贈与
当制度は、自分の子どもに対して住宅取得のための資金として最大1,000万円までの贈与が非課税になる制度です。
子供夫婦がそれぞれの親から1,000万円ずつ贈与を受ければ合計2,000万円の住宅取得資金が無税で確保できます。
ただし、この制度は令和4年4月1日現在のところ2023年12月末までの期限付きとなっていること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受けて居住開始することなどの要件があるため、利用時期は慎重に検討しましょう。
また、贈与できるのは「取得するための資金(現金)」であって、自宅である土地・建物を直接贈与することはできません。そのほか、適用する住宅や受贈者についてもいくつか要件があるため、注意が必要です。
教育資金の一括贈与
孫や子などが、祖父母や両親などから教育資金の一括贈与を受ける際に、1,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
対象となる受贈者は30歳未満の子や孫で、贈与者はその直系尊属(親や祖父母)に限られます。また、教育資金の非課税制度は暦年贈与と併用することが可能ですので、1,500万円を一括で教育資金として贈与したあとに、年間110万円以内の範囲で少しずつ財産を贈与していく、というような贈与計画も可能となります。
ただ、贈与された子や孫が30歳になるまでにその資金を使い切った際は贈与税はかかりませんが、30歳になった時点で教育資金を使い切っていなかった場合には、その残金に対して贈与税がかかることになります。
また、教育資金の非課税制度を適用している途中で贈与者が死亡した場合は、教育資金口座の残額が相続税の対象になります。
この制度も2023年3月31日までの期限付きであること、受贈者の前年所得が1,000万円未満であることなど、いくつか注意が必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与
孫や子などが、祖父母や両親などから結婚や子育て資金として贈与を受ける際に、1,000万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
このうち結婚のための費用は、300万円が限度額となります。
対象となる受贈者は18歳以上50歳未満の子や孫で、贈与者はその直系尊属(親や祖父母)に限られます。
受贈者が50歳になった時点で結婚・子育て資金に残額がある場合は、その残金に対して贈与税がかかることになります。
また、結婚・子育て資金の非課税制度を適用している途中で贈与者が死亡した場合は、結婚・子育て資金口座の残額が相続税の対象になります。
この制度も2023年3月31日までの期限付きであること、受贈者の前年所得が1,000万円未満であることなど、いくつか注意が必要です。
2.生前に行う相続の節税対策
生命保険の活用
相続税を極力抑えたい場合は、生命保険の活用を検討しましょう。生命保険は、保険の対象となる人(被保険者)が亡くなったときに、受取人に対して死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金で、契約者(保険料の負担者)と被保険者(亡くなった人)が同一人物で、受取人は相続人の場合は、相続税法上「みなし相続財産」となり、相続財産に組み込まれて計算されます。
つまり、生命保険の受取分にも相続税が課されるということになります。
しかし、生命保険には「非課税枠」というものがあり、具体的には「法定相続人の数×500万円」まで、相続財産である保険受取金から控除することができます。
例えば、法定相続人が4名いる場合は、2,000万円(500万円×4名)までの保険受取金については相続財産に含めないこととなり、その分相続税を抑えることができます。
現預金を不動産に変える
一般的に、土地や建物といった不動産は現預金と比較して相続税の負担が小さくなる仕組みとなっています。
例えば、手持ちの現預金を賃貸用不動産に換えて人に貸し出すことにより、資産の相続税評価額を低くすることが可能です。
更に、その賃貸用不動産を取得する際に銀行から借入れをすることにより借入金という債務、いわゆるマイナスの財産を作る(相続財産から控除する)ことができます。
これを活用することで、資産の相続税評価額を更に抑えることが可能になります。
さらに、居住用に使っている土地(宅地)などに対しては、相続税の評価額を最大で8割減らすことができる「小規模宅地等の特例」が使える場合があります。
ただし、最近の裁判例では、相続税の節税を前提とした不動産購入など極端な相続税対策は認められないという判決が出されているケースがありますので注意が必要です。
養子縁組により相続人を増やす
養子縁組を行うことにより、
- 相続人が増える
- 配偶者・子ども達以外の者に財産を承継させることができる
といったメリットがあります。
養子縁組により相続人が増えると、基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増加するため相続税の節税効果があります。
ただし、民法上は養子縁組の人数に上限はありませんが、相続税法上では制限があります。
実子がいない場合は養子ふたりまで、実子がいる場合は養子ひとりまでが法定相続人の対象となるため注意が必要です。
養子縁組は、相続税対策に一定の効果が期待できる場合もありますが、その反面、養子縁組が相続人同士の争いを招く争族につながってしまうという事例もあります。
養子縁組をする際には、メリットとデメリットの両方をしっかり確認しておきましょう。
3.相続税対策の税理士選び
上記でご紹介した方法以外にも、相続税の節税方法は数多くあります。
その中からそれぞれの相続財産や相続人の関係性等を考慮して最適な対策を組み合わせて行っていくことが重要になりますが、一般の方がご自身で判断するには難しく、早めに経験豊富な税理士に依頼することがベストでしょう。
税理士というと全ての税目に詳しいと思われがちですが、医者に内科医、外科医、眼科医という専門があるように、税理士にも得意分野があります。
したがって、他士業(弁護士、司法書士など)から紹介してもらったり、ホームページで相続税専門若しくは相続税申告の実績が豊富であることを明記している税理士から選択することが一般的です。
その際には、目先の節税対策の説明だけでなく、注意点や二次相続も考慮した説明なども含めて親身に相談に乗ってくれるなど、ご自身が信頼できる税理士に依頼するようにしましょう。